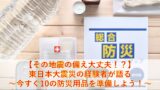2022年3月16日、23時34分、23時36分と2回続けて地震が発生しました。

2度の大地震
2022年3月16日 23時34分 1回目の地震

「もう寝ようか」と思ったそのとき、ゴゴゴゴという地響きとともに激しい揺れが襲ってきました。
慌てて起き上がり、テレビの電源を入れると、ちょうど緊急地震速報が流れ始めました。
揺れはますます激しくなり、テレビが倒れ、食器棚から食器が飛び出して割れる音が響きました。
妻と顔を見合わせ、ため息しか出ません。
子供は寝室で安全に避難しており、幸い私たちの寝室には倒れるものがなく無事でした。
さ~、どうしようかなと思っている矢先に、2回目の地震。
2022年3月16日 23時36分 2回目の大きな揺れと、再び襲ってきた恐怖

ほんの数分前、激しい揺れがようやく収まったかと思ったのも束の間、今度は地響きのような轟音が聞こえてきました。まるで3.11の時のように、家が大きく揺れ始めます。
緊急地震速報のけたたましい音が鳴り響き、全身に鳥肌が立ちます。この音は、私にとって大きな恐怖の象徴。
部屋の中は、まるで暴風雨に見舞われたように荒れ放題でした。
机の上にあったプリンターは倒れ、壁掛けの額縁は落下。冷蔵庫の扉が開き、ビールなどの飲料が床に散らばっています。
3.11の時は無事で済んだ食洗器までもが倒壊。冷蔵庫や家具は、数センチも元の場所から移動していました。
3.11の時よりも、今回のほうが部屋の中は大きな被害を受けています。この激しい揺れを感じながら、私の頭の中には津波の映像がよみがえりました。
我が家は内陸部なので大きな被害を受ける心配は少ないですが、あの巨大な津波の恐ろしさを考えると、沿岸部に住む人々のことが心配でなりません。
どうか、大きな津波が来ませんようにと、心から祈るばかりでした。
幸い、沿岸では大きな被害は無かったとのことで、安堵しました。
地震直後の行動
地震が起きたら、まず落ち着くことが大切です。慌てると怪我をする可能性が高まります。冷静に状況を判断し、安全な場所に避難しましょう。
地震が発生したら安全な場所に逃げる

地震はいつ、どこで起こるかわかりません。突然の揺れに慌てず、冷静に行動することが大切です。
家の中の場合
地震を感じたら、まず身の安全を確保しましょう。
- ガラスや食器など割れるものが近くにある場所から離れる
- 本棚や家具が倒れてくる可能性がある場所から離れる
- 頭を守るため、テーブルの下など頑丈な家具の下に隠れる
- 揺れがおさまるまで、その場から動かない
外出中の場合
外出中に地震に遭遇した場合は、以下の点に注意しましょう。
- 古い建物、ガラス張りの建物、工事現場など、倒壊の危険がある場所から離れる
- 電線や看板などが落ちてくる可能性がある場所から離れる
- 津波が発生する可能性がある場合は、高台や堅固な建物へ迅速に避難する
- 人ごみを避け、落ち着いて周囲の状況を確認する
地震発生時の注意点
- 緊急地震速報は地震が来る前に鳴るものと思いがちですが、実際には地震が始まってから鳴る場合もあります
- 地震後には余震が続くことがあります
- 津波警報が発令された場合は、必ず高台へ避難してください
本能的にテレビを支えてしまう

地震の恐怖の中、私たちは本能的に大切なものを守ろうとします。「テレビ」もその一つかもしれません。しかし、写真のように、必死に支えていても倒れてしまうことがあります。
なぜこんなにもテレビに執着してしまうのでしょうか?それは、テレビが私たちの生活に深く根ざし、また高価なものであるからでしょう。
しかし、地震の時は、どんなに高価なものでも、命には代えられません。テレビを支えている間に、より大きな危険にさらされる可能性もあります。
地震が起きたら、まず自分の身を守りましょう。テレビは、たとえ壊れてしまっても、あとで買い直すことができます。大切なのは、あなた自身と、あなたの周りの人たちの命です。
ガスを止める

地震が発生した際、ガスの取り扱いは特に注意が必要です。以下の点にご留意ください。
- 初期の小さな揺れ:感知したら、直ちにガス栓を閉めましょう
- 大きな揺れの場合:ガス器具に近づかず、安全な場所に避難してください
- やけどの危険性:慌ててガスを止めようとすると、熱湯や油がこぼれてやけどをする恐れがあります。落ち着いて、安全を確認してから作業を行いましょう
家族の安否確認
地震発生時、家族の安否確認は、以下の点に注意して行いましょう。
- 家族全員の安否確認:まずは、一緒にいる家族全員が無事に避難できているかを確認します
- 連絡手段の活用:電話、メール、SNSなど、利用できる全ての連絡手段を使って、離れている家族と連絡を取り合い、安否を確認します。特に、海や川にいる場合は、すぐに安全な場所へ避難するよう伝えます
- 遠方家族との連絡:実家など、遠くに住んでいる家族とも、こまめに連絡を取り、状況を把握します
次の地震に備える

地震はいつ、どこで起きるかわかりません。また、今回の様に、大きな揺れが何度も続く可能性があります。
一度大きな揺れが収まっても、すぐに安心せず、次の地震に備えることが大切です。
停電していなければ、テレビやラジオなどで最新の情報を収集し、状況を把握しましょう。そして、いつでも外に出られるように、以下の準備が大切です。
- 避難経路の確保:家具が倒れてきたり、物が散乱したりして、避難の妨げになる可能性があります。事前に、安全な避難経路を確保しておきましょう
- 靴の確保:慌てて避難するとき、素足ではガラス片などでケガをしてしまう危険があります。事前に、靴を手に取りやすい場所に置いておきましょう
- 情報収集:地震に関する情報はこまめに確認し、状況に応じて適切な行動を取ることが大切です
水の確保が大切です

地震などで水が止まってしまうと、日常生活に大きな影響が出ます。
- 飲み水:備蓄の水がない場合は、ペットボトルなどに水をためておきましょう
- トイレ:トイレの水を流せなくなります。大きなペットボトルやポリタンクに水をためておいたり、お風呂の残り湯を流すのに使いましょう
- その他:洗顔や歯磨きなど、水を使う場面がたくさんあります。これらのために、水を無駄なく使えるように工夫しましょう
地震が収まったら、落ち着いて
地震は一度で終わらないことがあります。何度も揺れる可能性があるので、焦らずに落ち着いて行動しましょう。
被害が大きい場合は避難所に行くことも検討してください。
部屋の被害状況を確認しよう!安全にチェックする方法
地震などのあと、部屋の中がどうなっているか心配です。まずは、落ち着いて身の回りの安全を確認しましょう。
怪我を防ぐために
- 足元にご注意を!:割れたガラスなど、足で踏んでしまうとケガをする恐れがあります。スリッパやサンダル、靴を履いてから確認を始めましょう
- 軍手があると安心:ガラスの破片を触る際に、軍手があると手を保護できます。もし、軍手がない場合は、厚手の布などで代用することも可能です
確認ポイント
- 割れたものはないか:窓ガラスはもちろん、鏡や食器など、割れていないか一つひとつ丁寧に確認しましょう
- テレビ周辺もチェック:テレビが倒れていないか、コードが切れていないかを確認します
- 片付けは後回し:まずは、部屋全体の状況を把握することが大切です。片付けは、安全が確認できてから行いましょう
玄関までの「逃げ道動線」を再確保

次の地震に備えるために、玄関までの避難経路を改めて確認しましょう。
落ち着いて行動できるよう、家族全員がスムーズに外へ避難できる動線を確保します。
トイレへの避難経路もあわせて確保しておくと、より安心です。
水漏れの確認
水漏れにご注意ください!
水道、お風呂場、トイレなど、水まわりの確認が大切です。水漏れがないか、以下の点をご確認ください。
- 蛇口周り:地震により蛇口が緩んでいる場合があります。また揺れで、ゆがみなどが発生し水漏れになっている場合がありますので確認しましょう
- 洗濯機:揺れにより洗濯機が移動している可能性がありますので、蛇口、排水口の水漏れの確認をしましょう
- トイレ:便器の底やタンク周りも、漏れていないか確認しましょう。
もし、水漏れを発見した場合には、すぐに水道の元栓を閉めて、状況に応じて管理会社や水道局にご連絡ください。
【マンションや賃貸にお住まいの方へ】
上の階からの水漏れに気付く場合もあります。天井や壁に染みやシミがないか、定期的に確認することをおすすめします。
ガスの元栓の確認
東日本大震災以降、多くの住宅に設置されている都市ガスの元栓は、大きな地震が発生した場合に自動でガスを遮断するようになっています。これは、地震によるガス漏れや爆発を防ぐための安全対策です。
そのため、地震後にガスを使用するためには、ご自身でガスの元栓を復旧させる必要があります。復旧の手順は、ガス会社から提供されている説明書に詳しく記載されていますので、その手順に従って作業を進めてください。
ただし、地震の被害が大きい場合は、ガスの配管などが損傷している可能性があり、ご自身での復旧は危険です。その場合は、無理せずガス会社に連絡して、専門のスタッフに復旧作業を依頼しましょう。
また、復旧作業を行う前には、必ず部屋の中を十分に換気してください。地震によってガス漏れが発生している可能性があります。ガス漏れに気づいたら、慌てず窓を開けて換気し、ガス栓を閉めてからガス会社に連絡しましょう。
外の被害状況を確認する

地震発生後、まずは身の安全を確保し、落ち着いたら家の周りも確認することが大切です。
周囲の状況確認
- 火事の有無:隣家など、火災が発生していないか周囲を確認しましょう
- 建物の被害:ご自身の住まいの外壁、屋根、そして建物周辺の地面に損傷がないか、注意深く観察してください
- 車の状態:愛車の状態も確認しましょう
損傷の記録
もし、建物や車に損傷が見られた場合は、修理や保険請求の際に役立つよう、必ず写真を撮っておきましょう。その後、安全に配慮しながら、片付け作業を進めてください。
【ポイント】
- 安全第一:危険な場所には近づかず、安全な場所から確認を行いましょう
- 記録の重要性:写真は、後の手続きで非常に役立ちます
- 専門家の相談:大きな損傷の場合は、専門業者に相談することをおすすめします
片づける前に、大切な保険請求のために被害があった箇所を撮影する

地震で家が損傷し、ご心労お察しいたします。まずは身の安全を確保し、落ち着いて対応しましょう。
保険請求のため、必ず写真撮影を
地震保険や家財保険にご加入の方は、片付けを始める前に、以下の手順で写真撮影を行うことをおすすめします。
- 家財の被害状況を撮影する
- 家具、家電、食器など、破損や汚れのある部分を全て撮影しましょう
- 特に、高額な品物や、使用年数が短いものは、詳細に記録しておくと良いです
- 建物の外壁、屋根、庭などの被害状況を撮影する
- ひび割れ、倒壊、浸水などの被害箇所を、複数角度から撮影します
- 庭の塀や門、植木なども忘れずに撮影しましょう
なぜ写真撮影が大切なのか?
- 保険金請求の際に必要:保険会社に被害状況を正確に伝えるために、写真が必要となります
- 被害状況の記録:後から「どこが壊れていたか」など、記憶が曖昧になるのを防ぎます
- 交渉の際に有利:保険会社との交渉の際、写真があると、よりスムーズに進めることができます
写真撮影のポイント
- 全体と部分:被害の全体像がわかるように、全体を撮影した後、破損箇所をクローズアップして撮影します
- 日付と場所:写真に撮影日と場所を書き込んだり、GPS機能付きのカメラを使用したりすると、より正確な記録になります
- 保存:撮影した写真は、安全な場所に保管し、紛失しないように注意しましょう
片付ける
部屋の中が散乱している場合は、まず人が安全に行き来できる動線を確保しましょう。大きな家具をどかしたり、倒れたものを片付けたりするなど、大きな作業から始めると良いでしょう。
地震後の片付けは大変ですが、この機会に部屋をすっきりさせるチャンスと捉えましょう。焦らず、少しずつ、そして家族みんなで協力して、快適な生活空間を取り戻しましょう。
片付けたい場所から少しずつ
動線が確保できたら、片付けたい場所から少しずつ始めてみましょう。焦らず、自分のペースで進めることが大切です。
この機会に断捨離を
地震をきっかけに、普段使っていないものや、もう必要のないものを処分するのも良い機会です。半年以上使っていない雑誌や本などは、思い切って手放してみましょう。
家族みんなで協力して
家族みんなで協力して片付けを進めると、短時間で作業を終えることができます。また、一緒に作業することで、絆も深まるでしょう。
保険請求

建物や家財に対しての保険請求ができる場合があります。
ご自分が加入している保険を確認しましょう。
わからない場合は保険会社へ連絡をしましょう!
地震保険の申請について
地震保険は、地震、噴火、津波といった自然災害によって住宅や家財が損害を受けた際に、その損害を補償してくれる保険です。
地震保険の加入について
- 火災保険とのセット契約:地震保険は、火災保険に特約として加入する形で契約します。地震保険単体での加入はできません
- 補償内容:火災保険では補償されない、地震や噴火、津波による建物の倒壊や家財の破損などが対象となります
建物の補償
- 保険金額:火災保険の契約金額の30%から50%の範囲内で設定できます。ただし、支払われる上限金額は5,000万円までとなります。
- 支払われる金額:建物の損害の程度によって、以下の割合で保険金が支払われます。
- 全損(建物の時価の50%以上): 100%
- 大半損(建物の時価の40%以上50%未満): 60%
- 小半損(建物の時価の20%以上40%未満): 30%
- 一部損(建物の時価の3%以上20%未満): 5%まで
家財の補償
- 保険金額:1,000万円まで設定できます。ただし、支払われる上限金額は、火災保険の保険金額の半分までとなります
- 支払われる金額:家財の損害の程度によって、以下の割合で保険金が支払われます
- 全損(家財の時価の80%以上): 100%
- 大半損(家財の時価の60%以上80%未満): 60%
- 小半損(家財の時価の30%以上60%未満): 30%
- 一部損(家財の時価の10%以上30%未満): 5%まで
地震・家財保険のススメ
地震・家財保険は、地震などの自然災害から住宅を守るための重要な保険です。
火災保険とセットで加入することで、万が一の際に経済的な負担を軽減することができます。ご自身の住宅の状況に合わせて、最適な保険金額を設定しましょう。
まとめ
地震はいつ起こるかわかりません。2011年の東日本大震災、そして2021年の大きな地震など、私たちは何度もその恐怖を味わってきました。
今回の記事では、東日本大震災を経験し、何度も大きな揺れを経験した私が、地震発生直後に最も大切なこととして「逃げる道の確保、次の地震に備える」を強調しています。
なぜ「逃げる道の確保」が大切なのか?
- 倒壊の恐れがある場合、避難の妨げになる:家具や物が倒れて避難経路が塞がれてしまうと、貴重な時間を失い、危険にさらされる可能性が高まります
- パニックになりやすい状況下で、冷静な判断を妨げる:慌ててしまうと、どこへ逃げればいいのかわからなくなり、適切な行動が取れなくなってしまうことがあります
地震発生直後に行うべきこと
- まず落ち着いて身の安全を確保する:家具の下などに潜り込み、頭を守りましょう
- すぐに逃げる道の確認をする:周りの状況を把握し、安全に避難できる経路を確保しましょう
- 家族と連絡を取り合う:家族全員の安否を確認し、避難場所を決めておきましょう
事前に準備しておきたいこと
- 家族で話し合い、避難場所や連絡方法を決めておく:地震発生時に慌てずに行動できるように、事前に家族で話し合い、避難場所や連絡方法を決めておきましょう
- 家具の固定や耐震補強を行う:家具の転倒や落下を防ぐため、家具の固定や耐震補強を行いましょう
- 非常持ち出し袋を準備する:水、食料、懐中電灯など、最低3日分の生活に必要な物を用意しておきましょう
最後に
地震はいつ起こるかわかりません。しかし、事前にしっかりと準備しておくことで、被害を最小限に抑えることができます。この記事が、あなたと大切な人の命を守る一助となれば幸いです。
大切なのは、お金や物よりも、人の命です。
生きていれば、何とかなる!