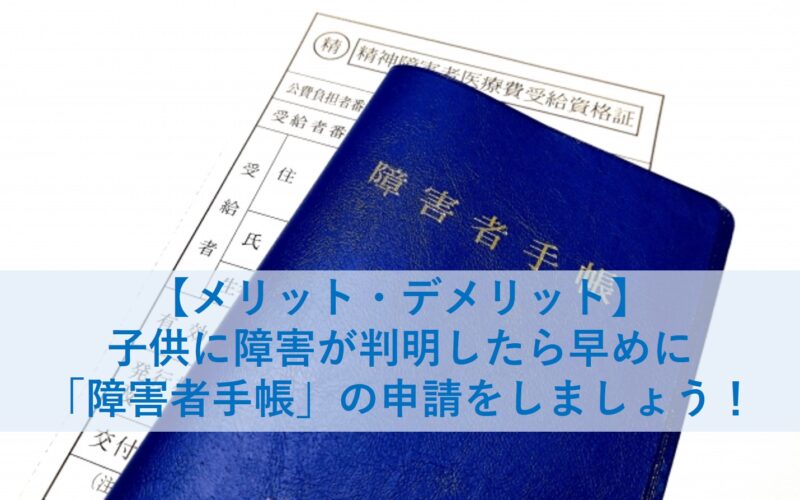現在、娘は軽い知的障害と精神障害があります。
娘は1歳になる時に痙攣発作が発生し、難治性てんかん「ドラベ症候群」と認定されました。
繰り返す痙攣発作により、脳へのダメージがあったみたいです。
親としてはショックです。
なぜ、うちの子が!?
はっきり言って、私は絶望しかありませんでした。
あんなことやこんなことができないと思うと眠れず涙が出ました。
一方、妻は全部を受け入れ、
「では、娘にこれから何をしてあげられるのだろうか?何ができるのだろうか?」
の切り替えでした。
今、できることは「楽しく遊べたり、学習できる環境」の整備。
妻が調べた結果、我が家には「療育手帳と精神障害者保健福祉手帳」が必要と判断し取得しました。
結論:早めに申請をしましょう!

手帳を取得できるのであれば取得しましょう!
障害と言う言葉にためらいがちですが、自分や子供の為に前向きに考えましょう。
手帳取得にはデメリットよりもメリットの方が多いです。
手帳の種類や手帳取得する事で受けれらるサービス等をまとめました。
これから手帳を取得しようと思っている方は是非一度、目を通していただければと思います。
障害者手帳とは?
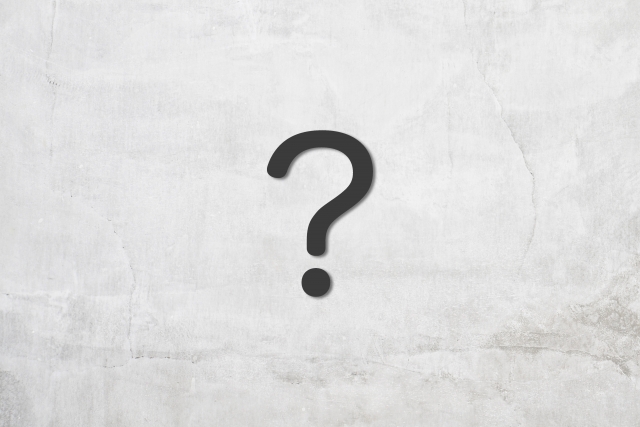
障害者の生きづらさを緩和し暮らしを支援してくれる障害者福祉制度があります。
この制度を利用するために、一定のハンディキャップがあることを証明できるのが障害者手帳です。
数字、またはアルファベットで障害の程度を表しています。
数字またはアルファベットの若い方が障害の程度は重くなっています。
手帳を取得すると、教育機関や就職の選択が広がったり、各種の手当や割引・税金の控除など経済面での支援を受ける事ができます。
障害手帳には3つに分かれます。
- 身体障害者手帳・・・身体障害者
- 療育手帳・・・知的障害
- 精神障害者保健福祉手帳・・・精神の場合
手帳を取得することでのメリット

子供の成長とともに必要となる「教育、就労支援」の分野で、サービスを受けるのに手帳の取得が条件だったり、国や自治体が実施している福祉手当の支給、各種の公的手当の税金の控除・減免などを受けることができます。
申請後、手帳の交付まで1ヵ月くらいかかるかもしれませんので、余裕をもって申請しましょう。
手帳取得することでのデメリット!
手帳を取得することでデメリットになることはありません!
一度、手帳を取得しても、必要性が無い場合は返却ができます。
手帳を取得していることを履歴書などに記載する義務がありません。
1つあるとしたら、障害者手帳を申請することによって、障害者であると認定されることへの抵抗感。
手帳に対する考えを少し変えて、今は障害があるからこの手帳のサービスを利用し、障害が治ったら返却をすればいいのです!
身体障害者手帳
身体(内部疾患を含む)に障害のある人が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合、本人(15歳未満は保護者)の申請に基づいて交付されます。
障害の程度によって1級から7級に分かれています。※交付は6級以上。ただし、7級は障害が1つあるだけでは交付の対象とならず、2つ以上重複すれば6級以上の障害と認定され交付の対象となります。
身体障害の場合は親が早く障害を認めることができたり、定期健診などで診断されることが多くあります。
障害がはっきりしたら、医師のアドバイスを受けて申請をしましょう。
身体障害者手帳交付対象となる障害
- 視覚障害
- 視覚または平均機能の障害
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓または呼吸器の機能の障害
- ぼうこうまたは直腸の機能障害
- 小腸の機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 肝臓の機能の障害
身体障害者手帳の申請時に必要なもの
手帳申請場所は市区町村の窓口
申請に必要な物
- 交付申請書 市区町村の窓口に用意されているもの
- 指定医が作成した診断書 所定の様式のもの
- 印鑑
- 本人の顔写真
- 委任状 ※本人が15歳未満の場合
- 本人のマイナンバーがわかる書類
- 保護者の身分証明書 ※本人が15歳未満の場合
療育手帳
知的障害者の療育手帳制度は厚生省が示したガイドラインに基づき、各都道府県などが実施要項を定めたものです。
各都道府県によって、手帳の名称、障害の等級や判定基準が違います。
18歳未満に発症し知能指数(IQ)がおおむね70以下が交付基準の目安です。
身体障害の場合と違い、申請時に医師の意見書などは不要です。
取得を検討する際は、市区町村の障害福祉の窓口に相談をしてみてください。
18歳未満の場合は児童相談所が判定機関になります。
心理判定員や小児科医が子供の様子を観察、知能テスト等を行ったうえで、障害の程度や手帳交付の必要性の有無を判定します。
各都道府県によって数年ごとに再判定が必要な場合もありますので、お住いの 市区町村の障害福祉の窓口にご確認ください。
療育手帳の申請時に必要なもの
手帳申請場所は地域によって違うので、市区町村の障害福祉の窓口に相談してから申請となります。
申請に必要な物
- 交付申請書 福祉担当窓口に用意されたもの
- 印鑑
- 本人の写真
- 母子手帳、幼少期の様子が分かる資料(18歳以上の場合)
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることで認定されます。
また発達障害者に対しても、障害者手帳を希望すれば、知的な障害のある人は「療育手帳」を取得でき、知的な障害の目立たない人は交付基準に該当すれば「精神障害者保健福祉手帳」を取得する事ができます。
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日です。
精神障害者保健福祉手帳交付の対象となる精神疾患
- 統合失調症
- うつ病
- そううつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- 発達障害者支援法などにより、「知的・精神」などの障害があれば、障害者手帳が交付されます。
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
精神障害者保健福祉手帳の等級数は3段階
- 1級・・・自立しての生活が困難。他人の手を借りなければ日常生活がおくれない
- 2級・・・常に人の手を借りなければならないほどはないが、日常生活が困難な状態
- 3級・・・障害は軽度だが、日常生活や社会生活で何らかの制限を受けている
発達障害とは?

不注意や言葉の発達の遅れ、コミュニケーション障害の傾向がある子は「発達障害」の可能性がある。
自閉症
- 言葉の発達の遅れ
- コミュニケーションの障害
- 対人関係・社会性の障害
- パターン化した行動、こだわり
アスペルガー症候群
- 基本的に、言葉の発達の遅れはない
- コミュニケーションの障害
- 対人関係・社会性の障害
- パターン化した行動、興味、関心のかたより
- 不器用
注意欠陥多動性障害(ADHD)
- 不注意(集中できない)
- 多動・多弁(じっとしていられない)
- 衝動的に行動する(考えるよりも先に動く)
学習障害(LD)
- 読む・書く。計算するなどが、全体的な知的発達に比べて極端に苦手
精神障害者保健福祉手帳の申請時に必要なもの
手帳申請場所は地域によって違うので、担当窓口に相談してから申請。
申請に必要な物
- 交付申請書 福祉担当窓口に用意されたもの
- 医師の診断書 所定様式の物
- 印鑑
- 本人の写真
・本人のマイナンバーカードがわかる書類
・代理人が申請する際は、代理人の本人確認ができる書類
国や自治体が実施している福祉手当
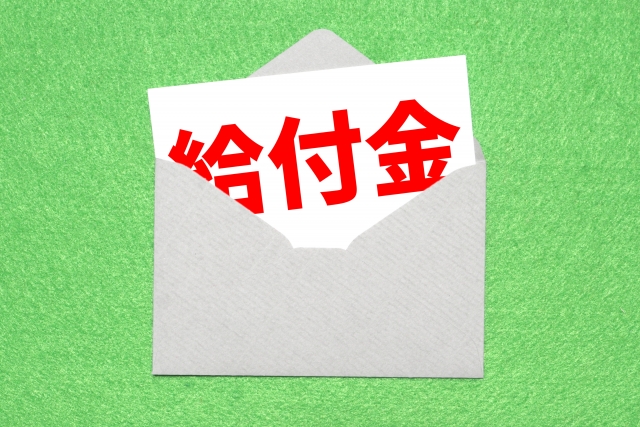
障害児・者の暮らしにくさをカバーする目的で国や自治体が支給する福祉手当です。
多くは障害者手帳を取得していることが前提です。
障害がはっきりしたら早めに障害者手帳を申請することをお勧めします。
保護者の所得制限などがあり、すべて申請による支給なのでお住いの市区町村に確認してください。
下記では仙台市の場合の手当を記載させていただきます。
特別児童扶養手当
目的:20歳未満で、心身に障害のある児童を監護している父又は母や、父母に代わってその児童を養育する方に手が支給されます。
支給月額:1級52,500円、2級34,970円
必要な書類:戸籍謄本または戸籍全部事項証明書、医師の診断書 ※障害者手帳不要
受給者対象外
- 児童が施設に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 申請者及び児童が日本国内に住所がないとき
※受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が、一定の額以上の所得がある場合は支給さない場合があります。
お住いの市区町村にお問い合わせください。
障害児福祉手当
目的
20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳Aの一部、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給されます。
支給月額:14,880円 ※仙台市
申請に必要な物
- 所定の様式の診断書(用紙は窓口にあります)
- 預金通帳又は貯金通帳(本人名義)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
受給者対象外
- 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所している方
- 障害を支給事由とする公的年金を受給している方
- 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません
特別障害者手当
目的:20歳以上で極めて重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給されます。
支給月額:27,350円
申請に必要な物
- 所定の様式の診断書(用紙は窓口にあります)
- 預金通帳又は貯金通帳(本人名義)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
受給者対象外
受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が、一定の額以上であるときは支給されません。
心身障害者医療費助成
目的:通院や入院などにかかった医療費のうち、保険診療による自己負担相当分の一部または全部を助成する制度。所得制限と、障害等級・種別による年齢制限があります。
助成内容
- 住民税課税者は1割負担(ただし上限額あり)
- 住民税非課税者は負担なし
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級、3級所持者
- 特別児童扶養手当1級、2級所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
※都道府県や市町村によって助成の内容や助成対対象者の範囲が異なる場合がありますので、お住いの地域の障害福祉窓口などにてご確認ください。
助成を受けられない場合
- 障害者本人、保護者、配偶者または障害者の生計を維持する扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹等)の所得が下記の所得制限の限度額を超えている方
- 生活保護を受けている方
心身障害者医療費助成に必要な書類
- 障害者手帳
- 資格登録申請書
障害者手帳による様々なサービス

手当のほかに手帳による「税金の控除、補助具購入時の負担の軽減、公共料金の免除・割引」のサービスがあります。
ご自身で確認し、必要なサービスを受けれる様に各窓口等にて申請をしてください。
所得税の障害者控除
納税者本人が障害者、障害者である親族を扶養している場合は、所得の控除が適用されます。
所得の控除としては27万円(一定以上の障害のある徳悦障害者は40万円)が所得金額から差し引かれます。
同一成型配偶者又は扶養親族が特別障害者で、常に同居しているときは、障害者控除として1人当たり75万円が所得金額から差し引かれます。
住民税の障害者控除
納税者本人、または控除対象の配偶者、扶養家族に障害がある場合は、障害者26万円、特別障害者30万円を所得金額から差し引きます。
また、特別障害者と同居している場合はさらに23万円が差し引かれます。
特別障害者とは
障害者のうち、特に重度の障害者(身体障害者手帳の1級もしくは2級、精神障害者保健福祉手帳の1級、重度の障害者と判定された人など)
相続の障害者控除
相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年に付き10万円(特別障害者20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。
贈与税の非課税
生活費などに充てるために一定の信託契約に基づいて障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その受託受益権の価額のうち特定障害者は3,000万円まで、特別障害者は6,000万円までが非課税になります。
※ただし、この非課税を受けてるためには、財産を信託する際に申告書を提出し、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければならない。
特定障害者とは
特別障害者および障害者のうち精神に障害がある障害者。
自動車税・軽自動車税減免
4月1日現在で所有している自動車税が45,000円まで減免されます。
自動車取得税の減免
300万円×該当する車の税率を上限に減免されます。
障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
地方公共団体が条例によって実施する障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金には所得税はかかりません。
少額貯蓄の利子等の非課税
身体障害者手帳等の交付を受けている場合、一定の預貯金等の利子などにつていは手続きを行えば非課税の適用を受ける事が出来ます。
金融機関の営業所などを経由して税務署長に提出します。
- マル優(預貯金)350万円までが非課税
- 特別マル優(公債)350万円までが非課税
補装具の助成
補装具とは、車いす・補聴器・盲人安全杖・義肢・歩行器などのことを言います。
補装具の交付・購入・修理で必要な費用の助成が受けられます。
負担額は下記の通り生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は0円です。
- 自己負担額は原則1割
- 生活保護生活保護世帯に属する者0円
- 低所得市町村民税非課税世帯0円
- 一般市町村民税課税世帯37,200円
※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外となります。
バリアフリー等のリフォーム費用の助成
重度障害者の在宅生活の支援や、介助者の負担軽減を図るため、住宅改造工事を行う場合に、工事費用の一部を助成。
段差解消、手すり・スロープの設置などのリフォームが対象です。
※市町村によっては助成の内容や助成対対象者の範囲が異なる場合がありますので、お住いの地域の障害福祉窓口などにてご確認ください。
公共料金等の減免・割引
- NHK受信料の免除
世帯全員が市区町村民税非課税の場合は全面免除。条件によっては一部免除。 - 水道料金、下水道料金の免除
特別児童扶養手当の受給者が対象。自治体によって異なります。 - 携帯電話料金の割引
基本料金が割引になるなどのサービスがあります。携帯電話会社によって異なります。
公共交通機関の割引
- JR運賃の割引
片道100km以上の乗車券が5割引。手帳に「一種」の記載がある場合は介護者も割引。介護者がいる場合は100km以内や、急行券の割引があります。 - 私鉄運賃の割引
鉄道会社に異なります。 - 路線バス
身体障害・知的障害の人は5割引。条件により介助者も5割引。 - タクシー
身体障害・知的障害・精神障害の手帳を提示すると10%割引 - 有料道路
障害者本人、あるいは障害者を同乗させている有料道路の通行料金が通常5割引 - 航空運賃
割引率は航空会社・路線によって異なります
自治体施設利用
自治体が運営する公園、博物館、動物園は障害者本人と付添人は無料が多いです。
※施設にご確認ください。
まとめ

「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」を提示することで、手当、税金の控除や免除・減免・そのほか様々な割引などが利用できるようになります。
障害者手帳は3種類
- 身体障害者手帳
- 精神障害者福祉保健手帳
- 療育手帳
障害者手帳の取得にはデメリットよりもメリットの方が多くあります。
障害者手帳によって受けられるサービスを知っていただき、いろいろなサービスを受けるようにしましょう。
障害者手帳の取得が可能かどうかは、各市区町村の自治体によって異なります。
取得する際は、必ず!お住まいの自治体に問い合わせをしてみてください。
わからない場合は障害者手帳を取得したいと話せばわかると思います。
申請をしようとするのが子供の場合、本人は申請できません。
親・保護者が申請をしなければなりません。
障害手帳の意味を十分に理解していただき必要か不要かのご判断をしてあげてください。
こんなに多くのメリットがあるのでちょっとでも必要かなと思ったら取得するべきだと思います。
本人、家族にとって魔法のカードです。
お金の面でもいろいろと余計にかかったりします。
魔法のカード取得で、少しでも金銭的な負担額を減らして楽しい生活を過ごしていただきたいです。
もちろん、我が家も毎日楽しく過ごしています!